「長期優良住宅って、結局どうなの?」
「取得した方がお得なの?それとも、しなくても大丈夫?」
インターネットで家づくりの情報を集めていると、このテーマで様々な意見が飛び交い、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
こんにちは、ぽよよ先輩です。理系大学院出身のメーカー開発職で、私自身もローコストメーカーで家づくりを経験しました。
今回は、そんな私の経験と分析を踏まえ、「長期優良住宅」の真実を、これから家づくりをされる方への「引き継ぎガイド」としてお伝えします。
この記事は、こんなあなたに読んで欲しい。
- 長期優良住宅って一体何?結局、取得した方がお得なの?
- 申請にお金はかかるの?
- メリットとデメリットを知りたい!
この記事を読めば、長期優良住宅制度の「正しい使い方」が分かり、住宅会社選びの無駄な時間と労力を省き、理想の会社を見つける手助けになるでしょう。
ぽよよ先輩の結論:長期優良住宅は「取得したほうがいい!」
いきなり結論からお伝えします。
私の意見としては、長期優良住宅は「取得すべき」です!
ただし、例外的に取得しなくても安心して良いケースもあります。
- 建物が構造計算(許容応力度計算)されている場合:耐震性能が極めて高く、長期優良住宅の耐震基準(等級2以上)をはるかに上回るレベルで設計されている場合です。この計算方法は、建物の柱や梁、壁にかかる力を詳細にシミュレーションするため、より確実な耐震性を確保できます。
- 床面積が足りず、そもそも取得できない場合:長期優良住宅には最低限の床面積の基準(一戸建ては75m²以上、少なくとも一つのフロアが40m²以上)があります。狭小住宅など、物理的にこの基準を満たせないケースでは、取得したくてもできません。
しかし、これらの例外を除けば、基本的には取得を推奨します。
なぜなら、長期優良住宅は単なる認定制度ではなく、「住宅会社の技術力や品質を見極めるための重要な指標」だからです。
つまり、それよりももっと大切なことがあります。
それは、「実際に取得するかどうかではなく、長期優良住宅に対応できる技術力があるかどうかを判別するために使うべし!」ということです。
これは、家づくりで失敗しないための、非常に強力な“武器”になると私は確信しています。
長期優良住宅の基本をおさらい:どんな家が認定されるの?
長期優良住宅とは、簡単に言うと「長く住み続けられる、質の高い住宅」を国が認定する制度です。
少子高齢化や環境問題が進む中で、政府は「つくっては壊す」住宅文化から「いいものを長く使う」ストック型住宅社会への転換を目指しており、その柱となるのがこの長期優良住宅制度です。
具体的には、以下の9つの項目をクリアする必要があります。
- 劣化対策: 数世代にわたり住宅の構造躯体(骨組み)が使用できること。(例えば、木材の防腐防蟻処理、床下空間の確保など)
- 耐震性: 極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルを低減する対策がとられていること。(耐震等級2以上が必須)
- 維持管理・更新の容易性: 構造躯体に影響を及ぼすことなく、給排水管やガス管などの点検・補修・交換が容易な構造になっていること。(例えば、点検口の設置、配管のインフラ化など)
- 省エネルギー性: 必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。(次世代省エネルギー対策等級4以上が必須)
- 居住環境: 良好な景観形成など、地域における居住環境の維持・向上に配慮されていること。(条例や景観計画に適合など)
- 住戸面積: 必要な居住面積が確保されていること。(一戸建ては75m²以上、少なくとも一つのフロアの床面積が40m²以上)
- 維持保全計画: 定期的な点検や補修に関する計画が策定されていること。(30年以上の計画期間で、少なくとも10年ごとに点検計画を定める)
- 資金計画: 維持保全計画に基づいた資金計画が適切に策定されていること。
- 災害配慮: 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されていること。(災害リスクの高い区域では、それを踏まえた計画が求められる)
これら9つの項目全てを満たすことで、長期優良住宅として認定されます。
戸建てにおいて特に重要な3つの項目
特に戸建てにおいて、私が重要だと考えるポイントは以下の3点です。
耐震性:耐震等級2以上
建築基準法で定められた耐震性能(等級1)の1.25倍の強度を持つことを意味します。消防署や警察署といった防災拠点となる建物と同等の強度です。
省エネルギー性:次世代省エネルギー対策等級4以上
断熱材の厚みや窓の性能など、建物の省エネ性能に関する基準です。
住戸面積:一戸建ては75m²以上、少なくとも一つのフロアの床面積が40m²以上
家族が快適に暮らすための最低限の広さを確保する基準です。
もう少し分かりやすく説明すると、「耐震等級が2以上」で、「次世代省エネルギー対策等級4以上」であれば、だいたいのケースで長期優良住宅として認定されます。
この2つの基準が、特に建物の基本性能を大きく左右するからです。
長期優良住宅は「ハイレベルな住宅ではない」と知るべし
ここで注意しておきたいのは、「次世代省エネルギー対策等級4」の基準です。これは平成11年に制定されたもので、断熱性能としては決して最高等級ではありません。
現在の断熱性能の高さのイメージ:HEAT20(G1/G2/G3) > ZEH基準 > 長期優良住宅(省エネルギー対策等級4)
HEAT20: 住宅の断熱性能を向上させることを目的に設立された団体が定める、より厳しい断熱基準です。G1からG3まで段階があり、G3が最も高性能です。
ZEH(ゼッチ): Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、使うエネルギーと創るエネルギーを合わせてゼロにする住宅です。そのためには、高い断熱性能が必須となります。
今の住宅基準から見ると、次世代省エネルギー対策等級4は簡単にクリアできるレベルです。
むしろ、断熱性能としては物足りないと感じる方もいるかもしれません
(数値で言えば、Ua値で0.87以下が基準です。現在の基準からすると、もっと低いUa値を目指すべきだと考えられます)。
つまり、長期優良住宅は決して「最高レベルの性能を持つ住宅」ではないという認識でOKです。
あくまで「最低限の良質な住宅」の基準と捉えるのが現実的です。
長期優良住宅は「住宅会社の実力を見極めるバロメーター」として使え!
長期優良住宅制度の真の価値は、その認定自体よりも、むしろ「住宅会社の技術力や品質、そして顧客に対する姿勢を見極めるためのツール」として使う点にあると私は考えています。
「長期優良住宅仕様で建てられますか?対応していますか?」と住宅会社に尋ねること。
これは、必要最低限の技術力を持たない会社を「ふるい落とす」ための、いわば“呪文”のようなものです!
もし「長期優良住宅には対応していません」と答える会社があれば、それはもう住宅会社の候補から外してしまって構いません。
なぜなら、長期優良住宅の基準は、現在の住宅性能を考慮すれば、決して高いハードルではないからです。
今の時代、長期優良住宅は、もはや「高い買い物」ではありません。
昔は認定を受けるための費用や、構造材のグレードアップなどで数十万円〜百万円単位のコストアップになると言われましたが、現在は多くの住宅会社が標準仕様で長期優良住宅の基準を満たせるようになっています。
ローコストで対応してくれる住宅会社も探せばたくさん見つかります。
「長期優良住宅で建てられますか?」と聞いて「はい、標準で対応しています」と即答する会社は、それだけの技術力とノウハウを持っている証拠です。
逆に、もし「長期優良住宅にするとコストアップします」と言う会社があったとしたら、それはもともとの建物の性能が極端に低いということです。
基本的な耐震性や断熱性が国の定める「最低限の良質な住宅」の基準にすら満たない可能性が高いわけです。
わざわざ、そんな長期優良住宅仕様を建てられない会社を、人生最大の買い物である注文住宅で選ぶ必要はありません。
(ちなみに、建売住宅でも長期優良住宅をクリアしている会社はたくさん存在します。建売でもクリアできる基準なのですから、注文住宅であればなおさらです。)
長期優良住宅の「弱点」も知っておこう:過信は禁物!
取得を強くおすすめする長期優良住宅ですが、もちろん弱点も存在します。
これらの弱点を理解せずに「長期優良住宅だから安心!」と過信するのは禁物です。
断熱性能の基準が物足りない
先述の通り、省エネルギー対策等級4は、現在の高性能住宅のトレンドから見ると時代遅れ感のある基準です。
より快適で光熱費を抑えられる家を求めるなら、HEAT20のG1/G2/G3水準やZEH基準を目標に、具体的なUa値(外皮平均熱貫流率)やC値(隙間相当面積)を確認すべきです。
気密性能に関する項目が皆無
長期優良住宅の認定基準には、「気密性能」に関する項目が一切ありません。
気密性能とは、家からどれだけ隙間風が入ってくるか、あるいは暖気・冷気が逃げるかを示す数値で、C値(単位はcm²/m²)で表されます。
C値が小さいほど高気密な家です。
高気密な家は、断熱材の効果を最大限に引き出し、冷暖房効率を格段に向上させます。
しかし、長期優良住宅で建てたとしても、気密測定を実施していなければ、隙間だらけの「スカスカの家」が建つ可能性もゼロではありません。
どんなに良い断熱材を入れても、隙間から熱が逃げてしまっては意味がないのです。
契約前に、その住宅会社が気密測定を「全棟実施しているか」「C値の目標値はあるか」を確認することが非常に重要です。
耐震等級3が必須ではない
耐震等級は2以上が基準であり、最高等級である3が必須ではありません。
耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の耐震性を持つことを意味し、より大規模な地震にも耐えうる頑丈さを備えています。
より安全性を高めるなら、構造計算(許容応力度計算)による耐震等級3を希望することをおすすめします。
木造2階建て以下の建物は「簡易計算」で済まされることが多いですが、許容応力度計算は構造の安全性を数値で確認するため、より信頼性が高いです。
これらの弱点を理解した上で、長期優良住宅をあくまで「最低限必要な基準」と捉え、さらに上の性能を追求していくことが、「本当にいい家」を建てるための秘訣です。
申請にはお金がかかる?実は「損はしない」
「長期優良住宅は申請費用が高いだけで、メリットがない」という意見を聞いたことがあるかもしれません。実際はどうなのでしょうか?
私の場合は、申請代金が10万円程度でした。
これは、設計事務所や行政書士に依頼した場合にかかる費用です。
一見すると大きな出費に見えますが、長期優良住宅を取得すると、様々な税制優遇が受けられます。
- 長期優良住宅取得による税制優遇
- 住宅ローン減税の優遇
一般的な住宅に比べて、住宅ローン減税の借入限度額が引き上げられます。
例えば、現在の制度では省エネ基準適合住宅が4000万円、長期優良住宅は4500万円(2024年末までの入居の場合)。
これにより、より多くの税額控除が受けられる可能性があります。
不動産取得税の控除額アップ
新築住宅の場合、不動産取得税の課税標準から1,200万円が控除されますが、長期優良住宅の場合は1,300万円に控除額がアップします。
登録免許税の軽減
住宅を新築した際の保存登記にかかる登録免許税の税率が軽減されます。通常0.15%のところ、長期優良住宅であれば0.1%に。また、土地の売買による移転登記も軽減される場合があります。
固定資産税の軽減期間延長
新築住宅の固定資産税は、一定期間半額に軽減されます。一般的な住宅は3年間ですが、長期優良住宅であれば5年間に延長されます(マンションは5年が7年に延長)。
これらの税制優遇を総合的に見ると、申請費用を差し引いても、結果的にプラスマイナスゼロか、少しお得になるケースがほとんどです。
特に、フラット35を利用される方であれば、金利の引き下げが適用されるため、総返済額で考えるとかなりお得になるケースもあります。(私はフラット35を利用しなかったので、そこまで金銭的なメリットは感じませんでした。)
結論として、申請にお金はかかりますが、減税などで結局損はしないケースもあります。(ただし、大幅に得をするわけでもありません。)
施主にとって、取得にデメリットはほぼなく、むしろ将来的な資産価値や売却時のアドバンテージを考えれば、取っておいて損はない制度だと断言できます。
「長期優良住宅はおすすめしない」という意見に惑わされるな!
インターネット上には「長期優良住宅はおすすめしない」という記事も見かけます。これには2つのパターンがあるでしょう。
- 長期優良住宅をクリアしていないのに「おすすめしない」と言う会社
- 長期優良住宅はクリアしているけど「おすすめしない」と言う会社
1.「クリアしていないのに」は論外
まず、「長期優良住宅に対応していません」「うちではできない」といった理由で「おすすめしない」と言う会社は、論外です。なぜなら、その会社は国の定める「最低限の良質な住宅」の基準すら満たせない技術力しかない、と言っているのと同じだからです。
そのような会社で、高額な注文住宅を建てるのはリスクが高いと言わざるを得ません。家づくりの候補から即座に外すべきです。
2.「クリアしているけどおすすめしない」は少数意見
次に、「長期優良住宅はクリアしているけどおすすめしない」という意見ですが、これは非常に少数派であり、私の経験上、そのような住宅会社には出会いませんでした。
私が住宅会社を回って「長期優良住宅に対応していますか?」と尋ねると、対応できる会社は「はい、標準で対応可能です」とあっさり答えるだけ。
無理に取得を推し進めることも、取得を嫌がることもなく、むしろ「当然のこと」として対応に余裕がありました。
これは、長期優良住宅の基準が、彼らにとってはすでに「標準」となっていることの表れでしょう。
一部でデメリットとして挙げられる意見についても、冷静に考えてみましょう。
「取得のために建物のコストが上がる場合がある」
前述の通り、「長期優良住宅にするとコストアップする」と主張する会社は、もともとの技術力や性能が低いと考えられます。
本当に「いい家」を建てている会社であれば、標準仕様で長期優良住宅の基準はクリアできており、追加コストは発生しないか、ごくわずかです。
もし追加コストが発生しても、それはあくまで「これまで低品質だったものを長期優良住宅の基準まで引き上げるためのコスト」と考えるべきです。
その分の性能向上は確実に得られますし、税制優遇で相殺されることも多いのです。
この意見は、高気密・高断熱、耐震等級3といったさらに上の性能を目指す際に、追加コストが発生することと混同されているケースも散見されます。
しかし、それは「長期優良住宅だから」ではなく、「より高性能な家を建てるから」かかるコストなのです。
「点検が必要になる」
長期優良住宅の認定を受けると、30年以上の維持保全計画を立て、少なくとも10年ごとに点検や修繕を行う必要があります。
これをデメリットと捉える意見もありますが、これは果たしてデメリットでしょうか?
家は建てたら終わりではありません。
健全に維持され、長く住み続けるためには、定期的な点検と計画的なメンテナンスが不可欠です。
点検が義務付けられることで、適切な時期にメンテナンスを行う習慣がつき、結果として家の寿命を延ばし、大規模な修繕費用を抑えることにも繋がります。
むしろ、点検計画を立てることで、将来的にかかるであろう修繕費を計画的に貯蓄するきっかけにもなります。
施主から見れば、これは「家を守るための健全な義務」であり、決してデメリットではないはずです。
最後に、長期優良住宅の申請代はかかりますが、減税等で損はしないため、施主としては取得にデメリットはほぼなく、「取っておいて損はない」という結論になります。
まとめ:「いい家」を建てるための羅針盤として長期優良住宅を活用しよう!
長々と説明してきましたが、結局のところ、長期優良住宅は、
「実際に取得するかどうかではなく、長期優良住宅が使える技術力があるかどうかを判別するために使う!」
これが、この制度の正しい活用法だと断言できます。
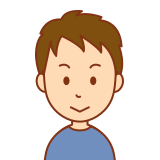
英語ができるかどうかの基準として、英検やTOEICがあるように
長期優良住宅という制度もいい家が建つかどうかの1つの基準かと思っています。
英検やTOEICの点数が高くても、英語ができない人もいるように、
長期優良住宅でも必ずしもいい家ではない。
いい家をつくるための最低限必要な基準という認識です!
〇自己紹介
30代半ば、2児の父。メーカー開発→インフラ事業企画へとキャリアを歩み、転勤&目先の給料UPに惹かれて転職したものの、仕事に苦しむ日々…。そんな私が唯一夢中になれたのが「家づくり」でした。
家づくり期間中は、毎日定時ダッシュで帰宅。仕事の開発は片手間に?、仕事で培った分析力を家づくりの研究にフルコミット!情報収集・見積もり交渉・住宅性能の比較など、施主視点での試行錯誤のすべてをこのブログにまとめています。
ちなみに育休は合計2年間取得。送り迎えから保育園会長までつとめています。(育児も本気!)





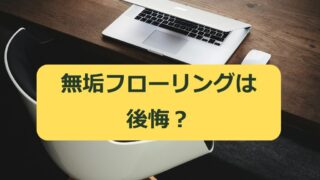
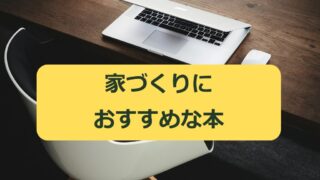



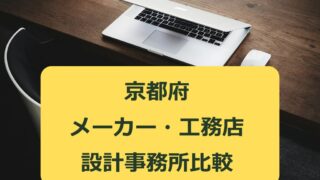

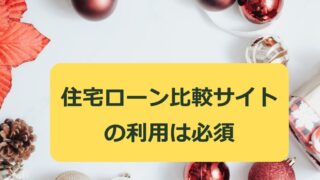
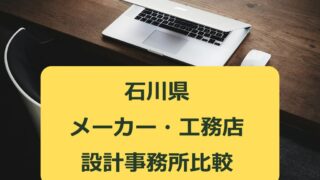


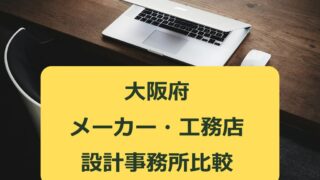
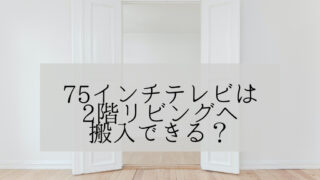


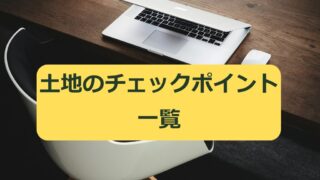


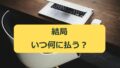
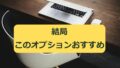
コメント