インフラ企業につとめる自分が、謎文化あるある書いていきます。
1. 資料の体裁と表現に異常なまでのこだわり
インフラ業界では、たかが確認資料、されど確認資料。
その作成には、なぜか魂を削るほどの熱量が注ぎ込まれます。
特に偉い人が見る資料となると、改訂回数は50回を超えることもザラ。
「帯の位置は上から何ポイント?」
といった、もはや肉眼では判別不能なレベルでのこだわりが炸裂。
正直なところ、「そこ、気になります?」と聞きたくなるようなポイントで修正指示が飛んできます。
夜中にTeamsで上司と一緒に「てにをは」の修正を延々と続ける地獄のセッションは、インフラ社員の通過儀礼とも言えるでしょう。
もはや実務よりパワーポイントの見た目が何より大切!という「見栄え至上主義」が蔓延しています。
さらに、プレゼン前には「国会議員か!」とツッコミたくなるような事前QA資料を作成し、ありとあらゆる想定問答を準備します。
そして、各役員を回る説明スケジュールという名のロジを作成し、資料作成と説明が、異様に重厚なのです。(中身は薄い?)
2. 敵は社外にあらず、社内にあり
インフラ業界で部長クラスの役職に就くと、その周囲の「忖度」具合が尋常じゃありません。
部長が出張するとなれば、移動の手配から会食のセッティングまで、まるでVIPツアーのプランナーのように綿密な準備が求められます。
もはや、外部のベンダーや顧客は二の次で、最大の敵は「社内の上司」という感覚に陥りがちです。
誰もが上司の顔色を伺いながら仕事を進め、社長なんて存在は「雲の上」どころか、もはや「神話の存在」です。
一方で、社外の人とのやり取りは意外とあっさりしていることが多く、「あれ?なんか逆じゃない?」と感じることも。
しかし、これがインフラ業界では「あるある」なのです。社内政治という名の壮大なRPGをクリアしていくことが、何よりも重要なのかもしれません。
3. 謎すぎる昇格試験
インフラ業界は多種多様な職種があるため、一律に能力を測ることが非常に困難です。
そのため、昇格試験はもはや「謎の儀式」と化しています。
テキストの丸暗記で乗り切る試験、何が評価されているのかさっぱりわからないディベート、誰が貢献したのか不明なグループディスカッション、そしてプレゼンテーション…。
なぜかその場にいる人にしかわからない「何か」で合否が左右されることも。
そしてさらに厄介なのが、部署ごとに昇格できる人数に「枠」があること。
そのため、「あの部署は昇格しやすいらしいよ…」「うちは枠が少ないから厳しいね…」といった不穏な情報が飛び交い、昇格が運任せになることも。
昇格の可否は、日々の努力だけでなく、謎の試験と部署ガチャによって決まる、壮大なミステリーです。
〇自己紹介
30代半ば、2児の父。メーカー開発→インフラ事業企画へとキャリアを歩み、転勤&目先の給料UPに惹かれて転職したものの、仕事に苦しむ日々…。そんな私が唯一夢中になれたのが「家づくり」でした。
家づくり期間中は、毎日定時ダッシュで帰宅。仕事の開発は片手間に?、仕事で培った分析力を家づくりの研究にフルコミット!情報収集・見積もり交渉・住宅性能の比較など、施主視点での試行錯誤のすべてをこのブログにまとめています。
ちなみに育休は合計2年間取得。送り迎えから保育園会長までつとめています。(育児も本気!笑)







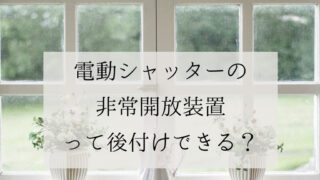
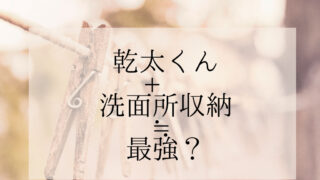





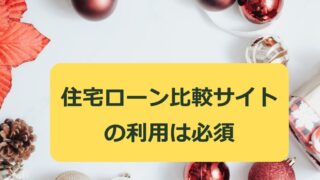
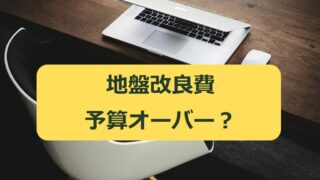
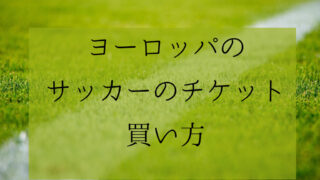
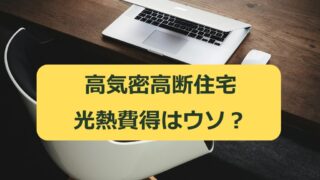
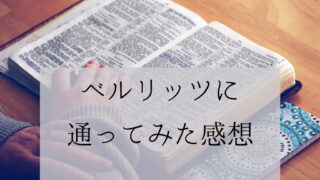
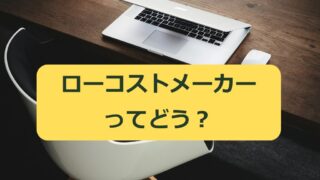
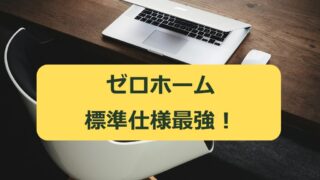

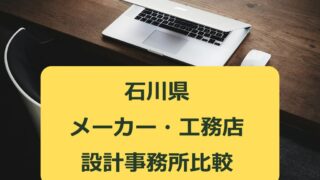
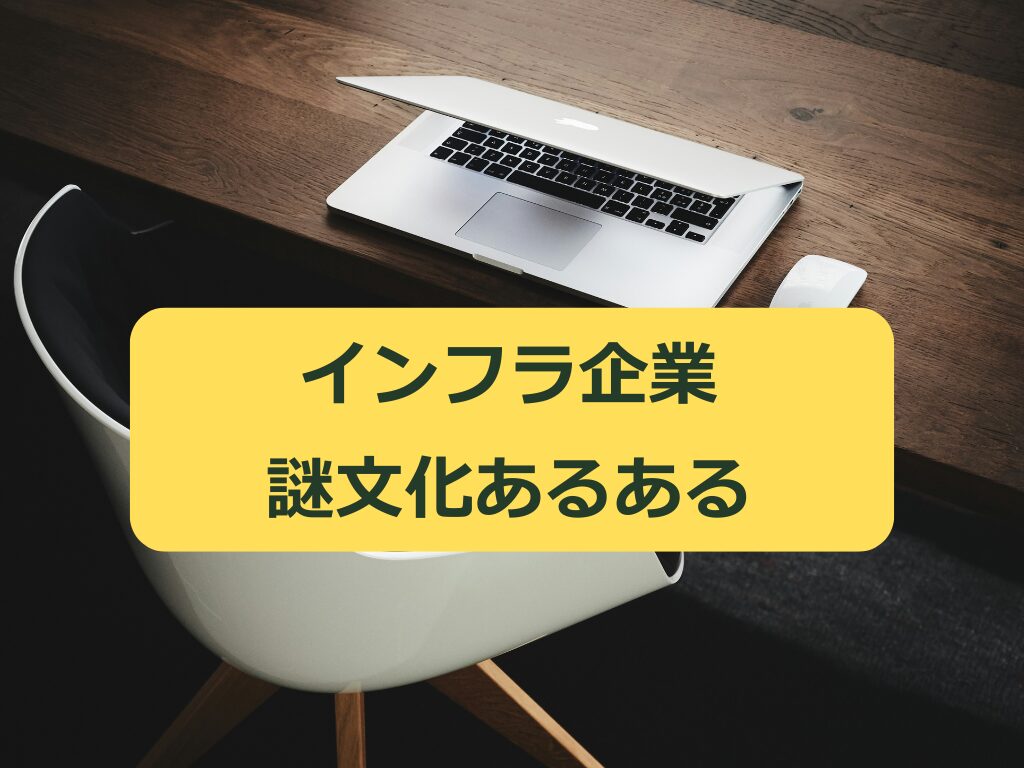


コメント